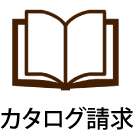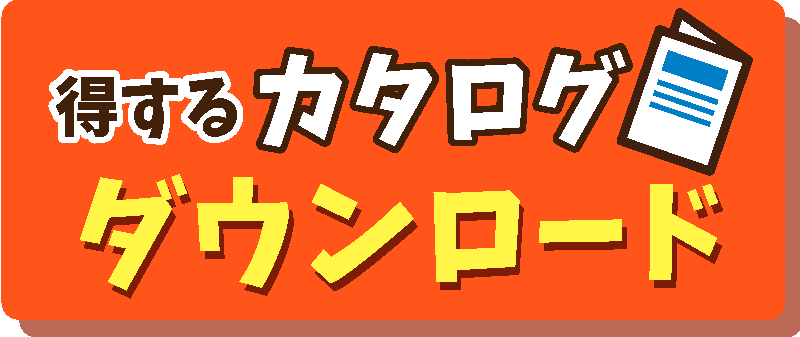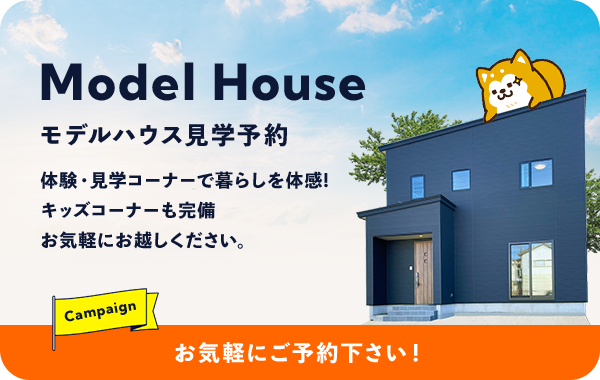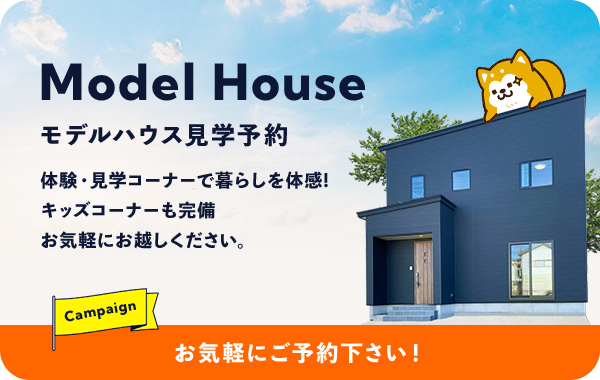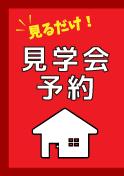家事がラクになる動線設計のコツ ~注文住宅だからこそ叶うストレスフリーな暮らし
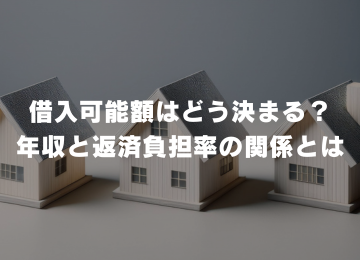
こんにちは!プラスホームです。
マイホームを手に入れるうえで、多くの方が最初に直面するのが「住宅ローンの借入可能額」。
「自分はいくらまで借りられるのか?」という疑問は、家づくりの資金計画を立てるうえで欠かせない出発点です。
でも、借入可能額ってどうやって決まるの?年収が高ければたくさん借りられる?
実はそこには、「返済負担率」という重要な指標が深く関わっています。
今回は、住宅ローンの借入額がどのように決まるのかを、年収や返済負担率との関係を交えてわかりやすく解説していきます。
無理のない資金計画を立てるために、ぜひ参考にしてください。
目次
- 借入可能額はどう決まる?年収と返済負担率の関係とは
- そもそも借入可能額ってなに?
- 返済負担率とは?
- 金融機関が重視する基準とは?
- 借入可能額と無理のない返済額は別物!
- 借入可能額を増やすには?
- まとめ
借入可能額はどう決まる?年収と返済負担率の関係とは
マイホームの購入を考える際に避けて通れないのが住宅ローン。
中でも「自分はいくらまで借りられるのか?」という借入可能額は、資金計画の出発点になります。
今回は、住宅ローンの借入額がどのように決まるのか、年収や返済負担率との関係を中心にわかりやすく解説します。
そもそも借入可能額ってなに?
借入可能額とは、金融機関が「この人なら無理なく返済できる」と判断した金額のことです。
住宅ローンは数十年にわたる長期の借入となるため、金融機関は収入の安定性や生活に支障なく返せるかを厳しくチェックします。
その際に重要な指標となるのが「返済負担率」です。
返済負担率とは?
返済負担率とは、「年収に対してどれだけローン返済に充てるか」の割合を示したものです。
住宅ローンの審査では、この返済負担率が大きな判断材料になります。
返済負担率の計算式
年間返済額 ÷ 年収 × 100 = 返済負担率(%)
例えば、年収500万円の方が年間120万円を返済する場合の返済負担率は、
120万円 ÷ 500万円 × 100 = 24%
となります。
金融機関が重視する基準とは?
金融機関やローンの種類によって審査基準は異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。
民間銀行ローンの場合:返済負担率は25〜35%以下が基準
フラット35の場合:年収400万円未満で30%以下、400万円以上で35%以下
この基準を超えると「返済負担が大きすぎる」と判断され、審査が通りにくくなります。
年収別の借入可能額の目安
返済期間35年、金利1.0%(元利均等返済)で試算した借入可能額の目安は以下のとおりです。
年収(税込) 返済負担率30%の借入可能額(概算)
400万円 約2,900万円
500万円 約3,600万円
600万円 約4,300万円
700万円 約5,000万円
※あくまで概算であり、金利・返済期間・他の借入状況により変動します。
借入可能額と無理のない返済額は別物!
ここで大切なのは、「借りられる金額=返せる金額」ではないということ。
将来の出費(教育費・車の買い替え・老後資金など)も見据えて、無理のない返済額でローンを組むことが重要です。
借入可能額を増やすには?
借入可能額を増やすには? 借入可能額を増やすには、以下のような方法があります。
・共働きでの収入合算(ペアローンや連帯債務)
・他の借入(車やカードローンなど)を減らす
・頭金を多めに用意する
・借入期間を長めに設定する(ただし総返済額は増加)
ただし、借入可能額を増やすことが目的ではなく、安心して返済できる金額を把握することが大前提です。
まとめ
住宅ローンの借入可能額は、年収と返済負担率のバランスによって決まります。
金融機関が提示する「借りられる上限額」にとらわれすぎず、将来のライフプランを踏まえて、自分にとっての“適正な借入額”を見極めることが何よりも大切です。
理想のマイホームを無理なく手に入れるためにも、まずはしっかりとした資金計画から始めてみましょう。
新潟県・新潟市・長岡市・上越市で新築一戸建て住宅・注文住宅を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!
プラスホームでは、新潟県・新潟市・長岡市・上越市でお客様にピッタリの新築一戸建て住宅・注文住宅を提案しています。
新潟県・新潟市・長岡市・上越市の新築一戸建て住宅・注文住宅はプラスホームにお任せください!!